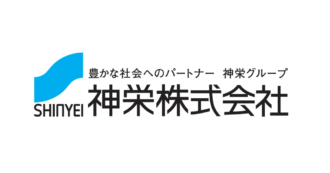四半期業績推移随時更新中
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
| FY2024.Q2 | 2023.09 | 23,995 | 1,416 | 5.9% |
| FY2024.Q3 | 2023.12 | 24,412 | 1,170 | 4.79% |
| FY2024.Q4 | 2024.03 | 22,508 | 647 | 2.87% |
| FY2025.Q1 | 2024.06 | 22,511 | 990 | 4.4% |
| (単位:百万円) | 決算期 | 売上 | 営業利益 | 営業利益率 |
| FY2017.Q4 | 2017.03 | 16,881 | 477 | 2.83% |
| FY2018.Q1 | 2017.06 | 17,331 | 979 | 5.65% |
| FY2018.Q2 | 2017.09 | 18,595 | 1,345 | 7.23% |
| FY2018.Q3 | 2017.12 | 18,531 | 1,040 | 5.61% |
| FY2018.Q4 | 2018.03 | 16,930 | 370 | 2.19% |
| FY2019.Q1 | 2018.06 | 16,317 | 372 | 2.28% |
| FY2019.Q2 | 2018.09 | 17,416 | 566 | 3.25% |
| FY2019.Q3 | 2018.12 | 16,524 | 20 | 0.12% |
| FY2019.Q4 | 2019.03 | 16,007 | -441 | -2.76% |
| FY2020.Q1 | 2019.06 | 16,131 | 226 | 1.4% |
| FY2020.Q2 | 2019.09 | 18,077 | 674 | 3.73% |
| FY2020.Q3 | 2019.12 | 17,872 | 241 | 1.35% |
| FY2020.Q4 | 2020.03 | 16,905 | -81 | -0.48% |
| FY2021.Q1 | 2020.06 | 16,038 | -337 | -2.1% |
| FY2021.Q2 | 2020.09 | 17,636 | 184 | 1.04% |
| FY2021.Q3 | 2020.12 | 19,916 | 1,128 | 5.66% |
| FY2021.Q4 | 2021.03 | 18,382 | 447 | 2.43% |
| FY2022.Q1 | 2021.06 | 18,644 | 857 | 4.6% |
| FY2022.Q2 | 2021.09 | 19,898 | 1,251 | 6.29% |
| FY2022.Q3 | 2021.12 | 20,560 | 1,026 | 4.99% |
| FY2022.Q4 | 2022.03 | 19,345 | 339 | 1.75% |
| FY2023.Q1 | 2022.06 | 19,388 | 226 | 1.17% |
| FY2023.Q2 | 2022.09 | 22,069 | 633 | 2.87% |
| FY2023.Q3 | 2022.12 | 22,740 | 66 | 0.29% |
| FY2023.Q4 | 2023.03 | 20,862 | -884 | -4.24% |
| FY2024.Q1 | 2023.06 | 22,143 | 952 | 4.3% |
| FY2024.Q2 | 2023.09 | 23,995 | 1,416 | 5.9% |
| FY2024.Q3 | 2023.12 | 24,412 | 1,170 | 4.79% |
| FY2024.Q4 | 2024.03 | 22,508 | 647 | 2.87% |
| FY2025.Q1 | 2024.06 | 22,511 | 990 | 4.4% |
沿革
1972年7月にハンバーガーの製造販売および販売指導を事業目的として東京都新宿区に株式会社モス・フード・サービスを設立、1973年11月にFC1号店をオープン、1984年6月に商号を株式会社モスフードサービスに変更した。
その後1985年11月に株式を店頭売買銘柄として日本証券業協会に登録、1986年6月に外食産業として初の全47都道府県出店を達成、1988年3月に株式を東京証券取引所市場第二部に上場、1991年2月に台湾1号店をオープン、1996年9月に東京証券取引所市場第一部に指定替え、2008年2月に株式会社ダスキンと資本業務提携した。
主にフランチャイズシステムによって飲食事業を展開している。国内2位の大手ハンバーガーチェーンである。
株主構成
参照日時:
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,972,000 | 9.5% |
| 紅梅食品工業株式会社 | 1,400,000 | 4.48% |
| 株式会社ダスキン | 1,315,000 | 4.21% |
| 株式会社ニットー | 1,214,000 | 3.88% |
| 日本生命保険相互会社|(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,209,000 | 3.87% |
| 山崎製パン株式会社 | 718,000 | 2.3% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 540,000 | 1.73% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234|(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 386,000 | 1.24% |
| モスフードサービス協力会社持株会 | 315,000 | 1.01% |
| 日本ハム株式会社 | 301,000 | 0.96% |
取締役会
参照日時:
| 役職名・氏名 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
| 取締役社長(代表取締役) 中村 栄輔 | 1958年6月13日 | 注5 | 12,000 |
| 取締役常務執行役員国際本部長 瀧深 淳 | 1962年10月14日 | 同上 | 1,000 |
| 取締役常務執行役員(リスク・コンプライアンス室担当) 福島 竜平 | 1963年2月25日 | 同上 | 19,000 |
| 取締役常務執行役員開発本部長兼新規飲食事業部長 内田 優子 | 1960年8月2日 | 同上 | 6,000 |
| 取締役上席執行役員営業本部長 太田 恒有 | 1971年12月14日 | 同上 | 3,000 |
| 取締役上席執行役員経営企画本部長 笠井 洸 | 1982年8月1日 | 同上 | 3,000 |
| 取締役 髙岡 美佳 | 1968年6月19日 | 同上 | - |
| 取締役 中山 勇 | 1957年10月12日 | 同上 | - |
| 取締役 小田原 加奈 | 1965年5月28日 | 同上 | - |
| 常勤監査役 永井 正彦 | 1958年10月4日 | 注6 | 4,000 |
| 常勤監査役 臼井 司 | 1961年4月15日 | 注7 | 6,000 |
| 監査役 藤野 雅史 | 1974年3月21日 | 注8 | - |
| 監査役 松村 卓治 | 1970年3月11日 | 注7 | - |
(注) 1.取締役髙岡美佳、中山勇及び小田原加奈は社外取締役であります。
2.監査役藤野雅史及び松村卓治は社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と執行役員の役割・責任の明確化による業務執行機能の強化を目的として2003年4月1日より「執行役員制度」を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、次の9名です。上席執行役員 安藤 芳徳 マーケティング本部長 執行役員 阿部 隆史 ストア事業本部長 千原 一晃 マーケティング本部副本部長兼マーケティング部長 川越 勉 経営サポート本部長 工藤 環 経営企画部長 金田 泰明 会長・社長室長 中野 秀紀 マーケティング本部副本部長兼デジタルマーケティング部長 西野入 博志 開発本部副本部長 平林 篤 営業本部副本部長兼東日本営業部長
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 氏名 生年月日 略歴 所有株式数(千株) 村瀨 孝子 1955年1月4日生 1997年4月 弁護士登録鳥飼・多田・森山経営法律事務所 入所 2005年1月 鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士 (現任) 2015年6月 ニッコー株式会社社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2020年6月 山一電機株式会社社外監査役 2022年6月 山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) -
5.任期は2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
6.任期は2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.任期は2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
8.任期は2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
※有価証券報告書から抜粋
代表取締役の経歴
代表取締役 取締役社長の中村栄輔氏は1958年6月生まれ。1988年6月同社入社、同社取締役執行役員、常務取締役執行役員等を経て、2016年6月同社代表取締役 取締役社長に就任(現任)した。
報告セグメント
2021年3月期からセグメント区分を変更し、国内モスバーガー事業、海外事業、その他飲食事業、その他の事業の4セグメントとしている。
2023年12月期 参照日時:
| セグメント | 売上高(百万円) |
| 国内モスバーガー事業 | 55,802 |
| 海外事業 | 12,574 |
| その他飲食事業 | 1,405 |
事業モデル
国内モスバーガー事業は国内で「モスバーガー」等の商標を使用した飲食事業、海外事業は海外で「モスバーガー」等の商標を使用した飲食事業、その他飲食事業は「マザーリーフ」「あえん」「MOSDO」等の商標を使用した飲食事業、その他事業は上記飲食業をサポートする衛生業や金融業などを展開している。
国内モスバーガー事業(直営店、FC店)が売上高、営業利益の大半を占めて収益柱となっている。国内モスバーガー事業の収益は直営店売上およびFC加盟店向け食材売上である。
決算短信によると2021年3月期末の店舗数は2020年3月期末比で、国内が25店舗減少の1,260店舗、海外が22店舗増加の413店舗となった。国内では直営店は都心立地型、FC店は郊外ドライブスルー型店舗が多い。海外は台湾286店舗、シンガポール47店舗、香港33店舗、タイ16店舗、インドネシア2店舗、中国10店舗、オーストラリア5店舗、韓国12店舗、フィリピン2店舗に展開している。

競合他社
- 2702 日本マクドナルドホールディングス(23年12月期売上高381,989百万円)
- 株式会社ロッテリア
- ファーストキッチン株式会社
- 株式会社フレッシュネス
連結の範囲
2021年3月期末時点でグループは、同社、子会社12社(うち9社が連結子会社、3社は非連結子会社)、関連会社14社(うち持分法適用会社7社)で構成されている。食品製造やアグリ事業を営む子会社や、食品衛生検査やレンタル事業を行うクレジット会社なども抱える。
強み・弱み
従来から、アンケート調査では「好きなハンバーガーチェーン」人気ランキング1位となることが多い。商品力に対する評価などブランド力の高いハンバーガーチェーンである。ただし店舗数や業績は伸び悩んでいる。
一方で、業績伸び悩みの状況が続いている。マーケティング・プロモーション戦略の革新、新規出店の推進、既存店の改装や競争力強化、店舗デザイン・レイアウトの変革、テイクアウト・デリバリーニーズへの対応、新商品や新業態の開発、不採算店の整理、店舗オペレーションの改善などで、規模拡大とともに収益性を高めることが課題だろう。2018年8月にモスバーガー店舗で発生した食中毒事故の影響で2019年3月期は大幅な営業・経常減益となり、親会社株主帰属当期純利益は損失を計上した。食の安全に関するリスクや、人件費高騰、感染症の影響による来店数の激減など、飲食店全般に共通するリスクを同社も抱える。
KPI
- 期末店舗数